ACL2023論文ざっと読み
Proceedings of the 61st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL2023)で気になった論文とそのメモ。
- Pre-trained Language Models Can be Fully Zero-Shot Learners
- Multi-CLS BERT: An Efficient Alternative to Traditional Ensembling
- Self-Adaptive In-Context Learning: An Information Compression Perspective for In-Context Example Selection and Ordering
- Cold-Start Data Selection for Better Few-shot Language Model Fine-tuning: A Prompt-based Uncertainty Propagation Approach
- Small Pre-trained Language Models Can be Fine-tuned as Large Models via Over-Parameterization
- Mixture-of-Domain-Adapters: Decoupling and Injecting Domain Knowledge to Pre-trained Language Models’ Memories
- Adaptive and Personalized Exercise Generation for Online Language Learning
- Distill or Annotate? Cost-Efficient Fine-Tuning of Compact Models
- Downstream Datasets Make Surprisingly Good Pretraining Corpora
- DrBERT: A Robust Pre-trained Model in French for Biomedical and Clinical domains
- TADA: Efficient Task-Agnostic Domain Adaptation for Transformers
Pre-trained Language Models Can be Fully Zero-Shot Learners
GPT3やGPT4ではZero shotでタスクを解けるが、実はBERTやRoBERTaなどのEncoderモデルも工夫すればZero shotで解けるのでは?という話。

普通だと上図のOriginal inputを入力して[CLS]トークンの出力から予測します。
この研究では、例えばトピック分類タスクの場合、後続のTemplateに答えさせたい内容を[MASK]トークンにして抽出するTemplateを作成します。
Original inputとTemplateを結合してLMに通し、[MASK]に何が入るかを予測させます。
トピック分類の場合SPORTS, SCIENCEなどの分類先のトピックが用意されています。
それごとにword embeddingの類似度から関連した語彙を集めます。
[MASK]が予測したトークンのlogitsについて、各トピックの関連語彙についてaggregationして、一番高い値になったトピックを予測結果とします。
Knowledgeable Prompt-tuning: Incorporating Knowledge into Prompt Verbalizer for Text Classification (ACL2022)とだいぶ近いが...
Multi-CLS BERT: An Efficient Alternative to Traditional Ensembling
普通のEnsembleと違って、CLSを様々な形になるように学習することで、Fine-TuningとInferenceが1回で済む、ということらしい。 EMNLP2020のQuickThought (QT、連続する2文から取った[CLS]の出力のnegative coine similarityを取るらしい)に割と依っている部分がありそう。 BERTのckptから学習を続ける形でマルチタスクをやっていそう。 図が分かりづらくて読む気が進まず、、、
Self-Adaptive In-Context Learning: An Information Compression Perspective for In-Context Example Selection and Ordering
In-Cotext Learning (ICL)において、あんまり似ていないというか役に立たない例をfilter outして、良いのを使おうという話。 SelectionはTopK (embeddingで近いもの)、RankingはMinimum Description Length (MDL)が良いらしい。 LLM時代にだいぶ必要となりそうなものなので、MDLについては勉強したほうが良さそう。
Cold-Start Data Selection for Better Few-shot Language Model Fine-tuning: A Prompt-based Uncertainty Propagation Approach
labeledデータがないcold-start時には、labelの分布などもわからないためbias等問題が発生しやすい。 それを解決するPATRONを提案。 さらに、情報量の多いサンプルを抽出するプロンプトベースの不確実性を伝播させる手法と、多様性と情報量のバランスを確保するpartition-then-rewrite (PTR)ストラテジーを提案。
各ラベルについて推定された確率が高いk個ずつのサンプルを取ってきておいて、そこから語彙の各単語について[MASK]に対して予測されやすい確率のバイアスの分布的なものを求める。 それを用いて入力に対する不確実性を表すエントロピーを算出できる式(論文中ではeq.5)を求められる。 サンプルxに対してk近傍(KNN)の距離を用いて不確実性と距離を考慮した式に修正する。 などと、不確実性とKNNを利用した距離をmixした式を構築して、距離が近すぎず不確実性も低いようなサンプルを取ってくる(という話のはず)。
Small Pre-trained Language Models Can be Fine-tuned as Large Models via Over-Parameterization
Fine-tuningのときだけLMをscaling upする。FFNでLoRAの逆(rank rを大きくする)的なこと。 精度は上がっているが、大きな上昇という感じはしない。
Mixture-of-Domain-Adapters: Decoupling and Injecting Domain Knowledge to Pre-trained Language Models’ Memories
TransformerのFFNにdomain用のadapterをくっつける FFNなのは、FFNに知識が蓄積されるから(introの2段落頭)。 adapterは2種類:domain用とtask用。 2.4の MoEの参考文献が多分参考になるので後で読む。

Stage 1では今までのpre-trainingコーパスに加えてDomain-specific knowledge (タスクのターゲット)を用いて学習する。 Domain-specific knowledgeのlossは普通のMLM loss。 old domainのFFNからのlossは、Domain Adapterと元のFFNの距離を小さくするためのloss。
Stage 2ではlabel付きのデータセットで学習するため、task-adapterとMoA Gateを追加して学習する。 task-adapterは各layerのタスクspecificな知識を学習し、MoA GateはDomain adapterの出力と元のFFNの出力をconcatして元のFFNの出力の形に合うようにlinear projectionする。
Adaptive and Personalized Exercise Generation for Online Language Learning
英語の学習をテーマに、生徒の知識レベルや難易度を予測しながら、excerciseを生成するタスクを解く。 Knowledge TracerとExcercise Generatorを順に更新していくところがELECTRAっぽい。 実問題を扱いつつ定式化が丁寧。
Distill or Annotate? Cost-Efficient Fine-Tuning of Compact Models
タイトルの通り大規模モデルからの蒸留と、アノテーションのどちらがよりコスト最適か?という話。 より効率的な推論のために蒸留するとのことだが、フロントエンドとか速度を要求されない限り大きいモデルのまま使えば良いような、、、 結論としては一部アノテーションしてそれ以降は蒸留するのが良いとのこと。
Downstream Datasets Make Surprisingly Good Pretraining Corpora
self-pretrainingは、下流タスクのコーパスで事前学習すること。 TAPTは下流のタスク以外のデータセットも入っているから違うらしい。 ELECTRAとRoBERTaで実験、ただcomputing resource的にハイパラがかなり小さめに設定されている。
TAPTとoffshelf(事前学習の元のコーパスで事前学習)はTAPTの方が良さそうに見えるが確実な傾向ではなかった。 self-pretrainingがoffshelfに比べて比較的良かった(これも全部ではないが平均するとoutperform)。 また、self-pretrainingとoffshelfをensembleしても多少よくはなる。 なお、ensembleの際はtemperature scaling (Guo et al., 2017)を用いている。
DrBERT: A Robust Pre-trained Model in French for Biomedical and Clinical domains
French domain-specific RoBERTa。 コーパスとモデルの公開がメイン?これで通るんだと思ってしまった、、
TADA: Efficient Task-Agnostic Domain Adaptation for Transformers
adaptationのためにembeddingだけをretrain。 embeddingのアンサンブルとして、単純平均やattention (meta-embedding)を比較。 tokenizerが変わったときの統合の仕方も3種提案 (Table 1)。ただこれはWordPieceでしか使えないことに留意。
DeBERTaV3: Improving DeBERTa using ELECTRA-Style Pre-Training with Gradient-Disentangled Embedding Sharing
本記事はDeep Learning 論文 Advent Calendar 2022の15日目です。
本記事では以下の論文について書きたいと思います。
※ 2022/12/16 式(2)が誤っていたため更新しました。
はじめに
DeBERTaV3は、2021年11月に第1版が公開されました。
Advent Calendar 2022なのに、2021年の論文を扱いますが、あまりDeBERTaについて書いている人がいなかったので、許してください、、、
DeBERTaV3は論文のタイトルの通り、2021年のICLRで発表されたDeBERTa: Decoding-enhanced BERT with Disentangled Attention(Open Review/arXiv、以下V1)のバージョン3にあたります。 V2までのモデルを継承しつつ、ELECTRAで用いられているGANライクな学習方法を、(GDESという手法で)更に改善することでV1(論文中ではDeBERTa)より下流タスクでのパフォーマンスを向上させています。 そのため、本記事ではV3以前のV1, V2について最初に触れます。 ここでは、BERTやRoBERTa、ELECTRAについては前提知識として割愛します。 ELECTRAについては【論文解説】ELECTRAを理解する (mm_0824氏)が参考になると思います。
※図は全てそれぞれの論文からの引用です。
V1
V1での新しい点は主に3つです。
- Disentangled Attention
- Enhanced Mask Decoder (EMD)
- Scale Invariant Fine-Tuning (SiFT)
このうちSiFTは巨大モデルを下流のNLPタスクに適用する際に、学習の安定性を保つために使われるアルゴリズムです DeBERTaの場合、パラメータ数が1.5Bの巨大モデルをSuperGLUEに適用する際に使われており、本文中でもfuture workとして位置づけられているためここでは割愛します。
Disentangled Attention
Disentangle Attentionは、各単語 (実際はトークン) を単語 (content) embeddingと位置embedding の2つのembedding の和で表します。
disentangle
...のもつれをほどく; ...を (もつれ・混乱などから) 解き放す etc. (ジーニアス英和大辞典より)
また、各transformer層のAttentionの(単語間の)重みを、この2つをもとにしたdisentangled matrixを用いて表します。 このアイデアにより、「深層」と「学習」という単語の依存性が、異なる2文の間で見られるより2つの単語が隣接していた方が依存性が強いことを表現できます。
位置 のトークンのベクトルを、内容(content)ベクトル
と位置
に対する相対位置ベクトル
を用いて以下のように表します。
このように、単語間のAttentionの重みは4つの行列の和で表されます。 左側から順にcontent-to-content, content-to-position, position-to-content, position-to-positionです。 先行研究では前者2つは使われているものの、DeBERTaにおいては3つ目を用いており、これが重要だとしています。 4つ目のposition-to-positionについては、あまり重要な付加情報がないため実装においてはremoveされています。 そのため、DeBERTaではcontent-to-content, content-to-position, position-to-contentの3つをAttentionの構成要素として用います。
これらをより詳しくAttentionの計算で見てみます。 ここでは、multi-headではなくsingle-headとして考えます。 ベースとなるのは一般的なself-attention (Vaswani et al., 2017)です。 一般的なself-attentionは以下のように表されます。
ここで が入力のhidden vector、
がself-attentionの出力、
がそれぞれ射影行列、
がattention行列です。
DeBERTaではcontentを表す の他に、相対位置を表す
を用意します。
このとき、相対位置を見に行く最大値を
とし、
とします。
になっているのは両側を見に行くからです。
また
はhidden statesの次元数で、BERTでいう768とか1024です。
先程の一般的なself-attentionのように、
と
を用いてquery, key, valueを求めます。
上式で、小文字のc, rはそれぞれcontent, relativeの意味です。
が存在しないのは、relative positionを使ったself-attentionにおけるvalueには文意などを取るために重要な意味が含まれていないためだと推察します。
これらを用いてattention行列 の要素
を求めます。
一気に複雑になりましたので要素を1つずつ見ていきます。
まずは から。
これはcontent-to-contentを表す要素です。
は
の
行目、
は
の
行目を表します。
次の は、content-to-positionに対応します。
ここで新しく
が出てきました。
はトークン
からトークン
への相対距離を表し、以下のように定義されます。
、つまり
が
より後方にある場合には0が、
、つまり
が
より前方にある場合には
が返ります。
また
と
の距離が
以下の場合は
が返ります。
の話題に戻すと、
は
の
行目を表します。
に対して
が
- 距離
より前方にあるときは
を
- 距離
より後方にあるときは
を
- 距離
の間にあるときは
を
使うということですね。
最後の はposition-to-contentに対応します。
は先程と同様に、
の
行目を表します。
このように求めた を用いて、self-attentionの出力は
と表します。
要素が3つ分あるため、 でスケーリングすることが特に大規模なモデルの安定化のために重要とのこと。
Enhanced Mask Decoder
DeBERTaでは、エンコーダーへの入力に絶対位置を入力せず、相対位置をDisentangled Attentionで使っています。 またBERTと異なり、Embeddingには位置に関連したEmbeddingを加算していません。 一方で、マスクされたトークンを当てる事前学習では、絶対位置がわからないと困ることがあります。 論文中の例では、"a new store opened beside the new mall"において、"store"と"mall"がマスクされ元のトークンを当てる例が挙げられています。 この場合、両方のトークンは"new"と相対位置が同じ(直後にある)ため、"store"と"mall"をモデルが判別することが困難になります。
そこで、DeBERTaでは最終層の代わりにEnhanced Mask Decoder (EMD)を導入します。
Enhanced Mask Decoderはパラメータを共有した2層のTransformer Layerからなります。
通常のTransformer層と同様に と
は
から持ってきます。
2層のうち1層目の
の入力の代わりに、
を用います。
ここで
は、BERTと同じPosition Embeddingとなります。
2層目の
の入力の代わりには、EMDの1層目からの出力を入力します。
事前学習とその結果
largeモデルは、6台のDGX-2を用い、合計96枚のNVIDIA V100を使っています。
バッチサイズ2k、1M stepsの学習で約20日とされているので、V100換算で1,920 GPU日になります。
baseモデルは4台のDGX-2 (合計64枚のV100)を使い、バッチサイズ2,048を1M steps学習させるのに10日かかっています。
換算で640 GPU日なので、ざっくりlargeサイズの1/3の計算量になります。
事前学習に使うテキストデータセットは、Wikipedia, BookCorpus, OPENWEBTEXT, STORIESを合わせて78Gになります。
RoBERTaやXLNetが160Gなので、その半分程度になります。
GLUEの結果は、平均的に各モデルより精度が高くなっています。
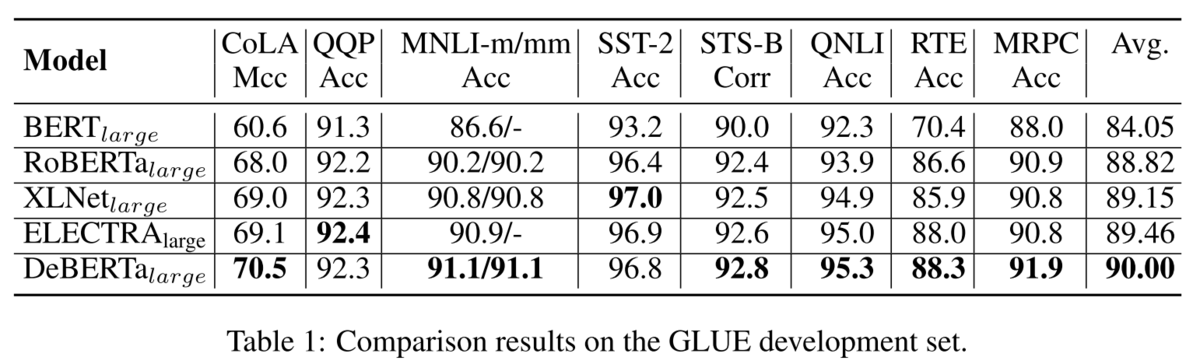
Ablationをしてみても、それぞれの要素が精度に貢献しています。
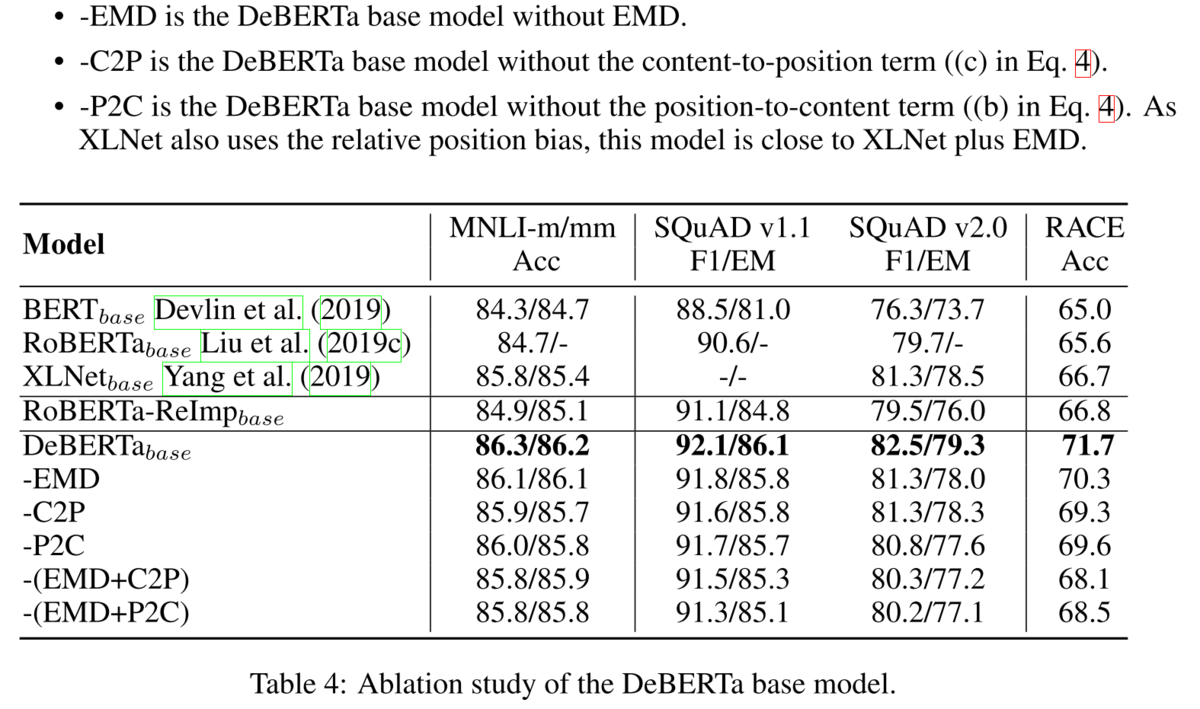
V2
V2で新しくなった点はGitHubで書かれています(論文では書かれていません)。 https://github.com/microsoft/DeBERTa#whats-new-in-v2 以下の5点が新しくなりました。
- Vocabulary: GPT2 tokenizerをsentencepiece tokenizerに変更し、語彙数を50kから128kに増やしました。
- nGiE(nGram Induced Input Encoding): 1層目のtransformer層の後に畳み込み層が追加されています。ablation studyについては今後追加する予定。
- 射影行列の共有。具体的には、V1における
を
と、
を
と共有します。これにより、パフォーマンスに影響することなくパラメータの削減が可能に。
- 相対位置をエンコードする際に、T5と似たlog bucketを使用します。
- サイズの大きい(900Mと1.5B)を構築したことで下流タスクでの性能を大幅に向上しました。
V3
さて、ようやくV3にたどり着きました。 書いている本人もV1にだいぶ時間がかかり、本題なのにすでに息切れしております(汗)
V3では、事前学習のタスクを変更しています。 従来のMasked Language Model (MLM)ではなく、MLMとReplaced Token Detection (RTD)という2つのタスクを行います。 MLMとRTDの2つのタスクを利用したモデルとしてELECTRA (arXiv/OpenReview, ICLR2020) があります。 ELECTRAを初めてお聞きの方は【論文解説】ELECTRAを理解する (mm_0824氏)が参考になると思います。 GANライクなGeneratorとDiscriminatorを持ち、GeneratorにMLMを解かせます。 Discriminatorでは、Generatorが予測したトークンが、元々のトークンから置き換わっているかの予測を行います。 MLMと異なり全トークンについて予測を行うため、計算効率を高めて事前学習を行えるというものです。 また、GeneratorとDiscriminatorでEmbeddingの共有 (Embedding Sharing, ES) を行うことでも効率性を高めています。
一方で、DeBERTaV3ではELECTRAのESの非効率性を指摘しています。
具体的には、Embeddingを共有することで、GeneratorとDiscriminatorの両方の学習で値を更新していくので、綱引き(tug-of-war)の状態になりやすいとのこと。
実際に、Embeddingの共有を行わない(No Embedding Sharing, NES)の場合より事前学習の収束が遅いことを示しています。
そこで、DeBERTaV3ではEmbeddingの共有はしつつも、Discriminatorではそれに差分を加えるGradient-Disentangled Embedding Sharing (GDES)を提案しています。
DeBERTaV1で提案されたDisentangled Attentionのように、Embeddingを共有しながらもDiscriminatorでは「2つにほどく」ようになっています。
具体的には、GeneratorのEmbeddingを としたときに、DiscriminatorのEmbeddingを
と表します。
ここで、 は勾配の伝播をしない(stop gradient)ことを表します。
つまり、Discriminatorの勾配は
によってのみ更新されます。
図で比較すると以下のようになります(左から順にES、NES、GDES)。
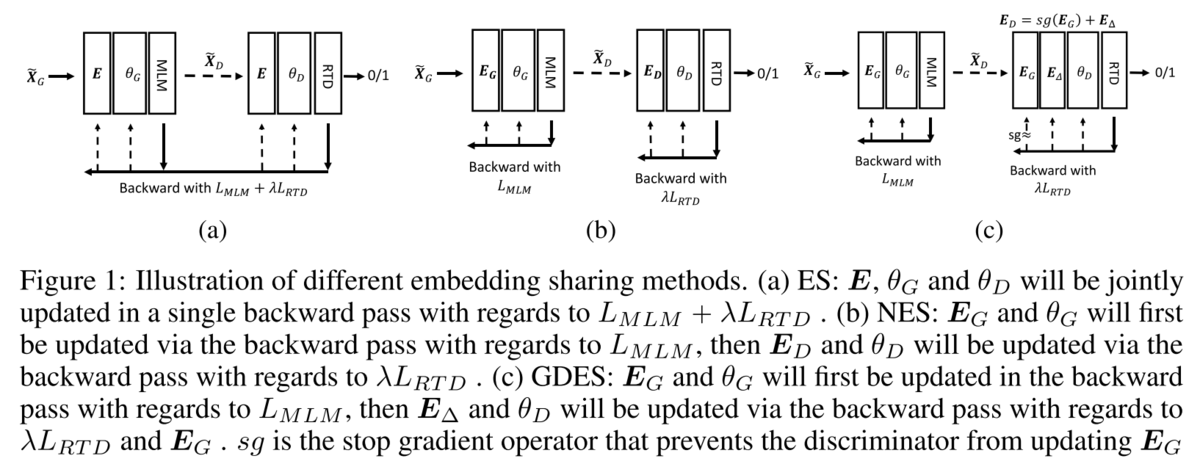
GDESの学習の順序としては、まずGeneratorのMLMのforwardとbackwardを行い、 を更新します。
次に、Generatorで作成された入力をもとにDiscriminatorのRTDのforwardとbackwardを行います。
backwardでは
のみが更新され、更新された後に
に加えられDiscriminatorの次のEmbedding
を構成します。
の初期値は0行列となります。
3つのEmbedding共有の手法の下流タスクでの性能を比較すると、GDESが最も性能が高いことがわかります。
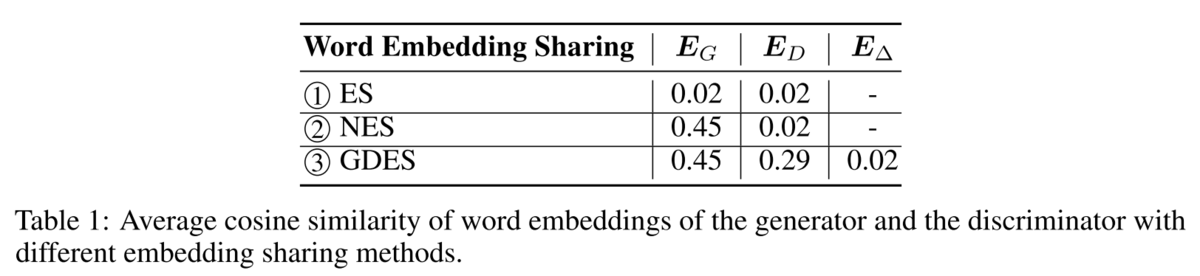
このGDESを用いてDeBERTaV3 largeを構築します。 ELECTRAと異なり、DeBERTaV3ではGeneratorがDiscriminatorの半分のtransformer層の数になる以外は全て同じモデル構造となります。 (ELECTRAではGeneratorがDiscriminatorの1/3~1/2のサイズになっています) こうして構築したDeBERTaV3は、DeBERTaV1を含む他のモデルに比べて更に高い性能を持っていることを示します。
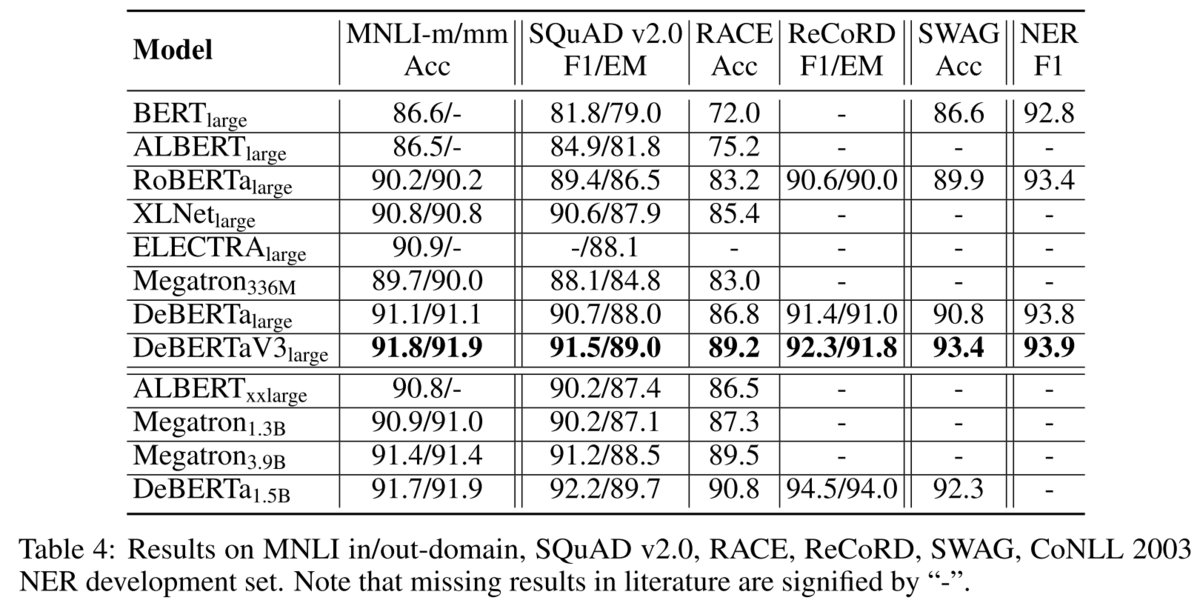
smallモデル(ELECTRAのsmallとは異なるサイズ)でも他のモデルと比べて高い結果を示すことが論文中のTable 5で示されています。
おわりに
DeBERTaV3の記事の予定が、DeBERTaV1が大部分となってしまいました。 DeBERTaV1, V2, V3ともにHuggingFaceでモデルが公開されているので、簡単に利用できるようになっています。 詳細なまとめはフリーで使える日本語の主な大規模言語モデルまとめ (HelloRusk氏)に譲りますが、日本語ドメインでは
がメジャーどころでしょうか。 (最後のELECTRAは私が構築したものです) 日本語ドメインで論文を書くときには最新のメジャーモデルで実験を行うことが求められがちなので、DeBERTaでも日本語モデルが公開されることを期待しております。 (私も作ってみようかしら、、、)
WikiExtractorが実はbulletを落としている
久々にWikipediaのdumpファイルを処理しようとWikiExtractorを動かそうとしたのですが、 GitHubからcloneしただけでは動かず。
ここにあるように、詳しくは調査していませんがPythonを3.7にしたら動きました。
それより大事なこととして、初期状態ではbulletが落ちてしまいます。
bulletまで落とさず残しておくには、L230~L260付近を主に2箇所(最初と最後)編集する必要があります。
私は著作と参考文献のbulletはいらなかったので、落としていますが入っても良い場合はif節が不要になります。
変更前:
# handle indents elif line[0] == ':': # page.append(line.lstrip(':*#;')) continue # handle lists elif line[0] in '*#;:': if Extractor.HtmlFormatting: i = 0 for c, n in zip_longest(listLevel, line, fillvalue=''): if not n or n not in '*#;:': if c: page.append(listClose[c]) listLevel = listLevel[:-1] continue else: break # n != '' if c != n and (not c or (c not in ';:' and n not in ';:')): if c: # close level page.append(listClose[c]) listLevel = listLevel[:-1] listLevel += n page.append(listOpen[n]) i += 1 n = line[i - 1] # last list char line = line[i:].strip() if line: # FIXME: n is '"' page.append(listItem[n] % line) else: continue
変更後:
# handle indents elif line[0] == ':': if 'title' in locals() and title not in ['著作.', '参考文献.']: page.append(line.lstrip(':*#;')) # continue # handle lists elif line[0] in '*#;:': if Extractor.HtmlFormatting: i = 0 for c, n in zip_longest(listLevel, line, fillvalue=''): if not n or n not in '*#;:': if c: page.append(listClose[c]) listLevel = listLevel[:-1] continue else: break # n != '' if c != n and (not c or (c not in ';:' and n not in ';:')): if c: # close level page.append(listClose[c]) listLevel = listLevel[:-1] listLevel += n page.append(listOpen[n]) i += 1 n = line[i - 1] # last list char line = line[i:].strip() if line: # FIXME: n is '"' page.append(listItem[n] % line) else: if 'title' in locals() and title not in ['著作.', '参考文献.']: page.append(line.lstrip(':*#;')) # continue
昨年Wikipediaから抽出したコードが残っていないのだけれど、多分抜け落ちているなあ、、、
生データを見ながら確認していくことは、やはり大事です。
Scale Efficiently: Insights from Pre-training and Fine-tuning Transformers
なにかのタイミングで著者のTwitterを見てICLR2022通ったところから見ました。
Excited to share that we have released 170+ pretrained transformer checkpoints of many different shape & sizes as part of our #ICLR2022 paper on "Scaling Transformers Efficiently" 😄.
— Yi Tay (@YiTayML) 2022年2月1日
Checkpoints: https://t.co/cowUl564Tt
Paper: https://t.co/BDG2aBss1I pic.twitter.com/LaHqANOGPU
arxiv自体は去年の9月に初稿が上がっていた模様。
ざっくり内容としては、OpenAIのScaling Laws for Neural Language Modelsを念頭に、
「とりあえずScale upすりゃええやろ、は本当かいな?」といったもの。
OpenAIの論文ではValidation Loss(確かPretrainingのだったのでupstreamにあたる)でしか議論されていませんでしたが、それを(downstream taskの)SuperGLUEのAccuracyで検証している。
モデルはGoogleなのでT5。
T5モデルのどこのパラメータを変えるかで接頭辞がついている。
- DM: model dimension
- FF: FFN hidden size
- NH: number of heads
- NL: number of layers

この図では、どのパラメータ(論文中ではつまみとも)を変えるかで性能の変わり具合が異なることを示している。
例えば一番右のNLは大きく変化するが右から2番目のNHはあまり変化がない。
ここでは、NL(layerなのでtransformerの図のdepth方向)をscaleした方がFF(width)をscaleするより効率が良いと報告している。
なので、同じパラメータ数という観点ではDeepNarrow(transformer層の数が多く(深く)、FFNの数を減らす(細く))するのが良いとしている。
もちろん無限に増やせば良いというわけではなく、層の数は32-36で収束する。
ちなみに、このDeepNarrowの考え方を採用したのがCharformerとのこと。
(また読むべきものが増える…^^;)
[2106.12672] Charformer: Fast Character Transformers via Gradient-based Subword Tokenization
こちらはオージス総研さんのページで実装と概要が述べられている。
はじめての自然言語処理 ByT5 と Charformer の検証 | オブジェクトの広場
DeepNarrowを実践した比較がTable 4になる。
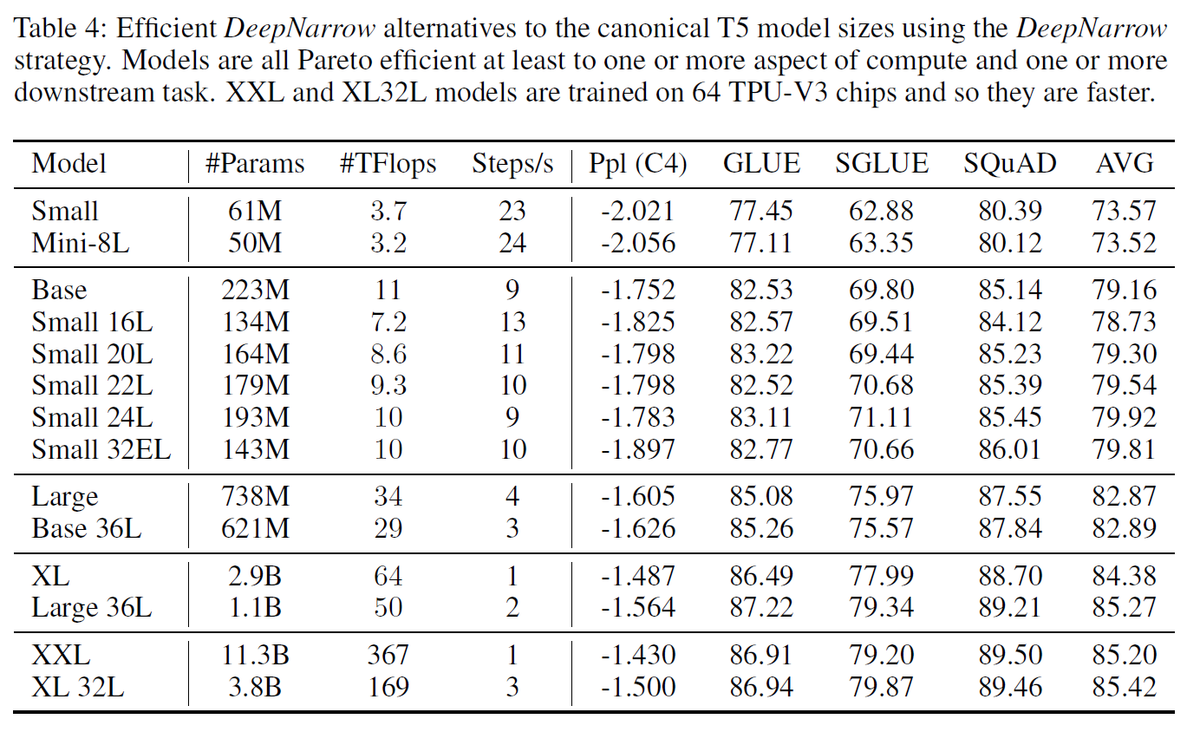
モデルのサイズを1段階小さくしても、layer数を増やすことでパラメータ数やTFlopsを少し小さくしながら同等またはそれ以上の精度を示している。
ただ、大規模モデルでは分散学習させることが多くなるが、深く細くすると並列化に限界が生じてしまうが、この点については考慮しない。
また層を深くすると勾配消失の問題が出てくるが、本論文の実験下では起きなかったとのこと。
Vision Transformer(ViT) や他のNLPタスクでもDeepNarrowの法則は成り立っている(Table 5-7)。
そのため、DeepNarrowは効率的に精度を高められる手法と言えそうだ。